「せいろって気になるけど、実際どうなんだろう…」
そんなふうに思ったことはありませんか?
蒸し料理がふっくら美味しく仕上がる、見た目もおしゃれ、健康にも良さそう。
そんな魅力がある一方で、「手入れが面倒そう」「収納スペースがない」「使いこなせるか不安」といった声もよく聞きます。
- そもそもせいとは?
- せいろにはどんな種類があるのか?
- せいろの代用品はある?
- せいろはどんな人に向いている?
せいろを買うかどうか迷っている皆さんが、自分にとって本当に必要かどうかを判断できるようになることを目指して、わかりやすくまとめました。
ぜひ最後まで読んで、納得のいく選択をしてみてください。
チェック>>楽天でせいろの売れ筋ランキングを見てみる
「せいろ」とは?基本の使い方と種類をわかりやすく解説
人気のせいろですが、意外と使い方やどういった種類あるか知らないことも多いですよね。
ここでは、せいろの基本的な使い方や種類について解説していきます。
せいろとは?
「せいろ」は、蒸気の力で食材を加熱する蒸し器の一種です。
主に木製や竹製の円形容器で、鍋の上に重ねて使います。
中華料理や和食でよく使われ、食材の旨みを逃さず、ふっくら仕上げるのが特徴です。
基本の使い方
- 鍋に水を張る
深めの鍋に2〜3cmほど水を入れ、沸騰させます。 - せいろを湿らせる
木製せいろは焦げ防止のため、使用前に水で軽く濡らしておきます。 - 食材を並べる
クッキングシートや蒸し布を敷いて、食材を重ならないように並べます。 - 鍋に重ねて蒸す
沸騰した鍋の上にせいろを乗せ、フタをして蒸します。蒸し時間は食材によって調整。 - 使用後はしっかり乾燥
洗った後は風通しの良い場所で自然乾燥。カビ防止のため、完全に乾かすのがポイントです。
せいろの種類
| 種類 | 特徴 | 向いている料理例 |
|---|---|---|
| 木製せいろ | 保温性が高く、香りがよく移る。見た目も美しい。 | 野菜・肉まん・和食全般 |
| 竹製せいろ | 軽くて通気性が良く、価格も手頃。 | 点心・中華まん・蒸し野菜 |
| ステンレスせいろ | 耐久性が高く、手入れが簡単。IH対応もあり。 | 魚料理・冷凍食品の温め直しなど |
サイズ選びのポイント
- 15〜18cm: 一人暮らしや副菜用にぴったり
- 21〜24cm: 家族向け、主菜も蒸せるサイズ
- 2段以上: 同時に複数の食材を調理したい人向け
せいろのデメリット
せいろを使ってみたいけど、扱い方や保管方法など気になる点は多いですよね。
ここではせいろのデメリットについて見ていきましょう。
収納スペースを取る
せいろはサイズが大きく、重ねて収納するにも高さが必要になります。
キッチンが狭かったり収納スペースがあまりない場合は、置き場所に悩むことも。
使う前に準備が必要
木製せいろは使う前に水に浸して湿らせる必要があります。
乾いたまま使うと焦げたり割れたりするリスクがあるためです。
調理時間が長くなることもある
せいろは鍋に湯を沸かしてから蒸していくので、お湯を沸かす分時間もかかります。
また、他の調理法に比べ調理温度が低いため調理時間が長くなりがちです。
手入れに少し手間がかかる(乾燥・カビ対策)
木製せいろは、洗剤では洗えず基本水洗いです。
もちろん食洗器では洗えません。
また、使用後すぐに乾燥させないとカビの原因にもなります。
関連記事:せいろの代わりになるもの5選!家庭にあるアイテムで本格蒸し料理!
せいろのメリット
ここではせいろのメリットをお伝えします。
ヘルシーで栄養価が高い
揚げ物や炒め物と違い、油を使わずに調理できるためカロリーを抑えられます。
また、茹でるよりも水溶性の栄養素が流出しにくいのもポイント。
素材の味を引き出す調理法
蒸すことで食材の旨みや香りが逃げず、調味料に頼らなくても美味しく仕上がります。
特に野菜や魚の繊細な風味が際立ちます。
調理中に手が空く
火にかけて蒸すだけなので、その間に他の作業を並行して進めることができます。
忙しい朝や夕食準備にも便利です。
洗い物が少なくてラク
鍋とせいろだけで調理が完結するので、フライパンや油汚れの洗い物が減ります。
木製せいろなら焦げ付きも少なく、手入れもシンプルです。
見た目が映える!食卓が華やかに
木の温もりがあるせいろは、料理をそのまま食卓に出しても絵になります。
普段使いでも重宝しますが、来客時や特別な日の演出にもぴったりです。
せいろの代用品|手軽に蒸し料理を楽しむ方法
「せいろが欲しいけど、収納や手入れが面倒そう…」そんな方に向けて、家庭にあるもので代用する方法や、便利な調理器具をご紹介します。
鍋と耐熱皿やザルで簡易せいろ代用
家庭にある鍋や深めのフライパンと耐熱皿やザルなどを組み合わせれば、即席の蒸し器として使えます。
使い方としては、
- 鍋や深めのフライパンに耐熱皿やザルを逆さにして台座を作る
- 水を注いで沸騰させ、蒸気が出たらさらに乗せた食材を置く
- 蓋をして食材に火が通るまで蒸す
こうやればせいろが無くても蒸し料理ができます。
ただし、蒸気の逃げやすさや火加減の調整には少し慣れが必要です。
電子レンジ調理器具で時短&省スペース
最近では、電子レンジで蒸し料理や焼き目までつけられる調理器具も人気です。
中でもレンジメイトプロは、電子レンジ専用なのに焼く・蒸す・煮るなど多機能で、忙しい人や一人暮らしの方にぴったりです。
特許技術により、レンジ調理でもしっかりと焼き目がつき、魚や野菜がふっくらジューシーに仕上がるのが特徴です。
しかも、洗い物も少なく、収納もコンパクト。せいろの代用品としてだけでなく、日常使いにも重宝します。
スチームケースも選択肢に
スチームケースも蒸し料理に向いています。
電子レンジで手軽に使え、デザイン性も高いので調理器具としてだけでなく、そのまま食卓に出すこともできます。
このように、せいろがなくても蒸し料理は楽しめます。
とはいえ、見た目や風味にこだわるなら、やっぱり本物のせいろも捨てがたいですね。
こんな人には「せいろ」がおすすめ!
せいろは一見、上級者向けの調理器具に見えるかもしれませんが、実は使い方次第で初心者にもぴったり。
ここでは、どんな人にせいろが向いているのかを具体的に紹介します。
素材の味を大切にしたい人
せいろは、食材の旨みや香りを逃さずに調理できるため、調味料に頼らず素材本来の味を楽しみたい人に最適です。
野菜や魚、肉まんなどがふっくら仕上がり、食卓の満足度がぐっと上がります。
健康志向・ダイエット中の人
油を使わずに調理できるせいろは、カロリーを抑えたい人や健康を意識している人にぴったり。
蒸すことで栄養素の流出も少なく、ヘルシーな食生活をサポートしてくれます。
忙しいけど料理は楽しみたい人
火にかけて蒸すだけなので、調理中に他の作業ができるのも魅力。
洗い物も少なく、段を重ねれば一度に複数品を調理できるため、時短にもつながります。
見た目や食卓の雰囲気にこだわりたい人
木製せいろは見た目も美しく、そのまま食卓に出しても映えるのがポイント。
来客時や特別な日の演出にも使え、料理の「魅せ方」にこだわる人にもおすすめです。
電子レンジ調理に飽きた人
「レンジ調理は便利だけど、味気ない…」と感じている人には、せいろの香りや食感の違いが新鮮に映るはず。
調理の楽しさを再発見できます。
まとめ
この記事では、せいろのメリット・デメリットについて解説しました。
せいろは、和食にも中華料理にもどちらでも使えてとても便利です。
また、素材本来のおいしさを引き出し健康志向の人にもピッタリです。
せいろを使って、食卓を豊かにしてみてはいかがですか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
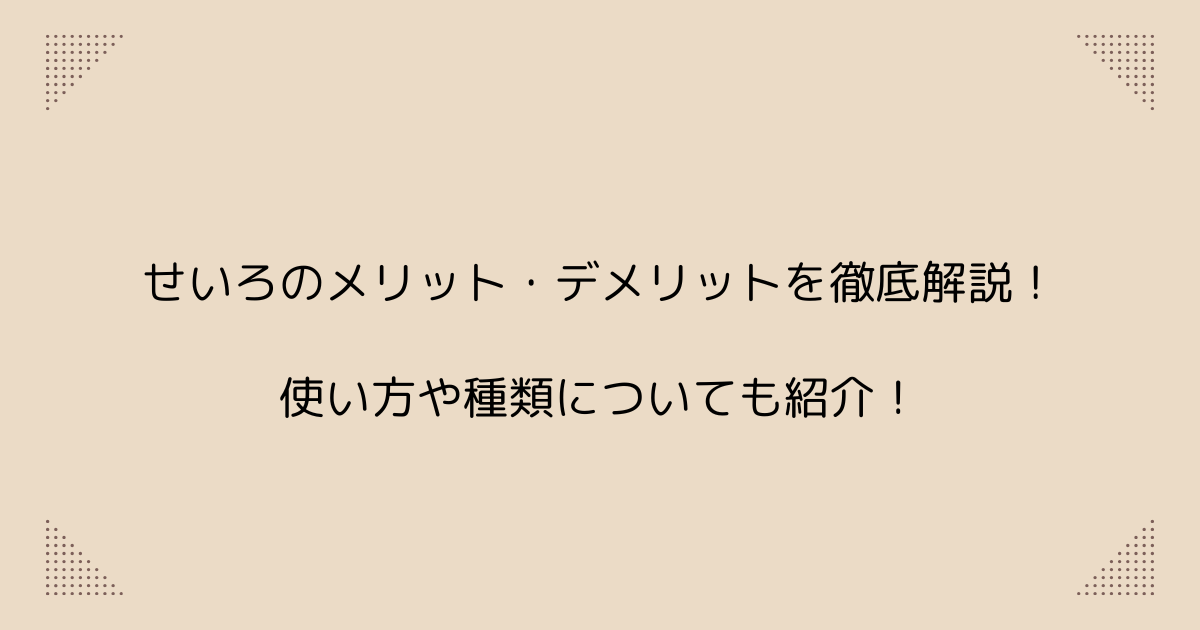
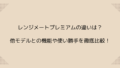
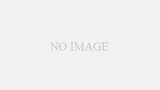
コメント